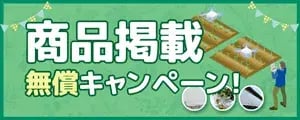近年、日本各地で大型台風や異常気象の発生が頻発しており、施設園芸用ハウス(ビニールハウス)の被害が深刻化しています。実際、ビニールハウスにおける被害の8割以上は台風や強風などの風害が主な要因とされています。これらの損壊や倒壊は農作物へ甚大な影響を及ぼすだけでなく、修復費用や収量減による経営への直接的な損失につながります。
本ブログでは、台風から農業用ハウスを守るための具体的対策について、被覆フィルムの選定ポイントから日常的な補強・点検の要点まで、専門的な視点で詳しく解説します。
強風に強い被覆フィルムの選び方
ハウスの屋根や側面を覆う被覆フィルムの種類は、耐風性および耐久性に大きな影響を与えます。日本の施設園芸分野におけるフィルム主要材の採用状況は、以下の通りです(jgha.com 大規模施設園芸・植物工場 共通テキストより)。
| 被覆資材 | 現在の使用比率(日本) | 特徴・耐久性など |
|---|---|---|
| 農業用ビニールフィルム(農ビ) *塩化ビニル樹脂系 |
約42% | 柔軟で張りやすく高い透明性。保温性も優れるが耐用年数は約1~2年程度と短い。紫外線で劣化しやすく頻繁な張替えが必要。近年はより耐久性に優れた農POフィルムへの需要増。 |
| 農業用ポリオレフィンフィルム(農PO) *ポリエチレン・EVA系 |
約46~47% | 強度・耐候性に優れ現在最も普及。紫外線劣化が少なく耐用年数は約3~5年と長い。軽くてベタつかず作業性も良好。防滴・防塵など機能付加製品も多い。高強度ゆえフィルムが裂けにくく強風でも飛ばされにくいが、その分ハウス骨組みに高い強度が求められる。 |
| 農業用フッ素樹脂フィルム *ETFEフィルム等 |
約5% | フッ素系樹脂製の高機能フィルム。耐久性が非常に高く15年以上の長期使用が可能。汚れが付きにくく透光性も抜群。初期コストは高価だが、張替え頻度が少なく長期的メリット大。強靭だが極端な暴風では他の資材同様に損傷リスクあり。 |
以上のように、現在は農POフィルムが主流であり、耐候性・耐久性の観点からも注目されています。農ビ(塩ビフィルム)は価格面で有利ですが寿命が短く、また焼却時に有害な塩素ガスを発生させ処分面の課題も指摘されます。一方、フッ素フィルムは少数派ながら耐用年数の長さで群を抜いており、台風常襲地帯や長期運用を見据えた高価値作物栽培などで採用されています。
強風対策としては、より厚手で引張強度の高いフィルムを選ぶことが有効ですが、その際はハウス骨組みも相応に強化することが重要です。例えば、「農ビから農POへの張替え」で耐風性向上が期待できますが、後述するように骨組み補強も合わせて行うことで初めて効果を発揮します。
また、古く劣化したフィルムは強風時に破れやすく危険です。台風シーズン前に被覆材の劣化や破れ箇所がないか点検し、必要に応じて新品に張り替えるか補修テープで応急処置をしておきましょう。
台風に備えるハウス構造の補強ポイント
堅牢なハウスを実現するためには、被覆フィルムと骨組みの双方を適切に強化することが不可欠です。特に高強度な被覆資材へ変更した場合、骨組みにかかる風荷重も増加するため、構造面での補強が必須となります。
以下に、台風や強風被害を未然に防ぐための具体的な補強・対策ポイントを整理しました。
- 開口部の封鎖(戸締りの徹底)
台風接近時にはハウスの出入口、側面、天窓など全ての換気口を確実に閉鎖し、堅固に固定してください。これにより、風の侵入口を遮断し、屋内の気圧上昇による屋根の持ち上げ(いわゆる屋根の吹き飛び被害)を防止します。「風通しを良くしよう」と両妻面の戸を開放する行為はかえって逆効果となり、内部に風が流入することで急激な内圧上昇を招き、フィルムの破損や骨組みの浮き上がりリスクが大幅に高まります。特にパイプハウスでの強風時には一瞬で全壊する危険があるため、この点は厳重に注意してください。 - 骨組みの補強(筋交い・タイバー設置)
ハウス内部に筋交い(ブレース)やタイバー(張り材)を追加することで、フレーム全体の剛性を向上させます。具体的には、アーチパイプと母屋(棟)を斜め材で連結しX型に補強する方法や、アーチと側柱をT字型に結ぶタイバーを設置する手法が考えられます。これらの簡易補強であっても、未実施の場合と比較して耐風強度に大きな差が生じます。加えて、妻面(ハウス端部)の構造的弱点が認められる場合には、妻面にも斜め筋交いを追加し、風圧による奥行き方向の倒壊リスクを低減させることが有効です。なお、これらの対策は専門業者による本格的な骨材補強ほどの大規模施工を必要とせず、生産者ご自身でも比較的容易に実践できる強風対策技術です。 - アンカー・固定具で基礎強化
強風時にハウス全体が浮き上がったり横滑りしたりしないよう、地盤への確実な固定を再確認してください。パイプハウスの場合、脚部が地中で緩んでいると、強風により抜けやすくなるため注意が必要です。必要に応じてアンカーペグやウェイトなどの補強資材を追加し、固定力を強化しましょう。特に台風時は豪雨による地盤の緩みが発生しやすく、パイプの保持力が低下しがちです。台風前には脚部の固定状況を点検し、必要なら再度しっかりと差し込み、補強杭を増設するなど、基礎強化対策を徹底してください。 - ハウスバンド・留め具の点検
ハウスのフィルムを固定しているハウスバンドや金具類に緩みがないか事前に点検してください。特に屋根や側面に設置されている押さえバンドは経年で緩みやすいため、台風前には必ず増し締めを行い、フィルムを確実に固定してください。必要に応じてバンドを増設することも有効です。側面部はバンドの緩みや巻上げパイプの揺動によるフィルム損傷が生じやすい箇所ですので、側面バンドの本数増設や巻上げパイプの固定など、適切な補強措置を講じてください。フィルムの固定に用いるスプリングやパッカーなどの留め具についても、緩みや外れがないかを確認し、不具合があれば速やかに交換・増設を実施してください。 - 防風ネットの活用
ハウス外部や開口部への防設置は、強風対策として有効な手段です。ハウス全体をネットで覆うことは難しいものの、例えば風上側の妻面前面に防風ネットを張ることで、直接的な風圧を効果的に緩和できます。また、巻上げ部(側面下部)の開口部にネットを設置することで、万が一フィルムが剥離した場合でも、風の内部への流入を一定程度抑制することが可能です。防風ネットは風速の低減効果が実証されており、施設園芸分野の強風対策技術として各地の専門マニュアルでも広く推奨されています。 - 周辺の整理と排水対策
ハウス周辺に資材や工具、ポリ桶など飛散しやすい物品が放置されていると、強風時にこれらが飛ばされてハウスを損傷させる要因となります。台風接近前には不要物を整理・撤去し、移動が困難な機械類や燃料タンクはロープなどで確実に固定してください。加えて、大雨への備えも重要です。ハウス周囲の排水溝は事前に掘り直しや泥の除去を行い、排水経路を確保しましょう。必要に応じて土のうを設置するなど、冠水防止策も併せて講じてください。これにより、豪雨による浸水で作物が被害を受けたり、地盤沈下で基礎が緩むリスクを低減できます。台風対策として、排水整備は必ず事前に実施してください。 - 換気扇の活用
ハウス妻面に換気扇が設置されている場合、台風時には換気扇を稼働させ、内部を負圧状態(やや真空状態)に維持することで、フィルムのばたつきや剥離を抑制し、風圧による飛散リスクを低減できます。ただし、停電時には換気扇が機能しないため、この方法への過度な依存は避け、停電発生時の代替手段もあらかじめ検討しておくことが重要です。 - 日常の点検整備
台風直前だけでなく、日常的にハウスの点検・整備を徹底することで、強風被害リスクを大幅に低減できます。特に骨組みのサビや劣化は構造強度低下の主因となるため、柱脚など錆びやすい部分は定期的に研磨・除錆(ケレン作業)を行い、亜鉛系塗料などによる防錆補修が有効です。また、緩んだボルトや亀裂・ヒビの入った接続部材などの損傷箇所は、早期に交換・修理し、ハウス全体を常に最良の状態に維持することが、予防保全と被害最小化につながります。
これらの対策を総合的に講じることで、ハウスの耐風・耐久性を大きく強化できます。特に、台風の接近前に迅速かつ確実に対応できるチェックポイントを以下にまとめましたので、ご活用ください。
台風前チェックリスト(事前に確認・対策すべき項目)
- フィルムの状態
たるみや破損、劣化がないかを点検し、問題箇所には補修テープによる対応を行い、重大な損傷が確認された場合は速やかな張り替えを検討してください。 - 固定バンド・留め具
ハウスバンドや金具類に緩みがないかを確認し、必要に応じて増し締めや追加設置を行ってください。側面換気パイプも確実に固定してください。 - 戸締りの確認
出入口ドア、サイド・天窓はすべて施錠し、クランプ等で固定して、風の侵入経路を遮断する措置を徹底してください。 - 補強資材の準備
筋交い用パイプ、ロープ、アンカー、支柱等の補強資材をあらかじめ用意し、必要箇所に的確に取り付けてください。状況に応じて防風ネットやブルーシートも活用してください。 - 周辺環境の整備
ハウス周囲の飛散しやすい物品を整理・固定し、排水溝の点検や泥詰まりの除去を実施してください。土のう等も用いて浸水対策を講じてください。 - 非常時への備え
停電発生時に備えて発電機や非常用電源を準備し、台風通過後すぐに換気や灌水を再開できる体制を整えてください。 - 保険の確認
万一に備え、農業共済(NOSAI)の施設共済等、ハウス向け保険への加入状況を確認してください。保険証券の保管場所もあわせてご確認ください。
超大型台風への対応策と緊急時の措置
近年、想定を超える規模の暴風雨を伴う超大型台風の発生が報告されています。最大瞬間風速がビニールハウスの耐風設計限界(一般的に秒速20数メートル程度)を大幅に上回る場合、万全を期した対策を講じていても被害を完全に回避することは難しくなります。そのため、極端な気象条件下における緊急対応についても把握しておくことが重要です。
- フィルムの一時撤去
栽培期間外であれば、被覆フィルムを全面的に撤去することが最も効果的な手段です。特にパイプハウスで収穫作業が終わっている場合は、台風到来前にフィルムを外して骨組み単体の状態とすることで、パイプの変形や倒壊のリスクを大幅に低減できます。現場では「最大風速25m/sを超える場合は被覆ビニールを撤去する」という判断が定着しつつあります。なお、栽培中などでフィルムの撤去が困難な場合でも、状況に応じて一部フィルムを切開し強風を逃がす最終手段も検討されます。その際は人的安全確保を最優先してください。 - 鉄骨ハウスの導入検討
長期的な対策として、強風被害が頻発する地域ではパイプハウスから鉄骨構造ハウスへの転換も有効です。鉄骨ハウスは基礎コンクリートを有し、構造的な堅牢性に優れるため、適切な対策と組み合わせることで被害の防止・軽減効果が期待できます。初期投資は高額になるものの、頻繁な修理や張替えによるコスト・労力と比較し、中長期的にはコスト効率に優れるケースもあります。現在パイプハウスをご使用の場合も、補強(筋交い追加や部材交換等)リフォームによって耐風性を強化することが可能です。地域の気象特性や予算に応じて、専門業者へのご相談を推奨いたします。
【参考:ファーマーズサポートネット - 耐風型ハウス設計施工企業のご紹介】 - 園芸施設共済(保険)への加入
いかなる対策を講じても自然災害による損害リスクをゼロにはできません。ビニールハウスの損壊等に備えて農業共済(NOSAI)等の施設共済へ加入することも重要です。保険加入によって、万一の際の復旧費用負担を軽減できます。公的支援が適用される災害(自治体の罹災証明等)もありますが、リスクマネジメントの観点から保険は非常に有効な備えとなります。
おわりに
台風大国日本において、農業用ハウスの台風対策は不可欠な営農スキルと言えます。被覆フィルムでは現在主流の農POフィルムを活用しつつ、骨組み補強や日頃のメンテナンスを徹底することで、強風による被害リスクを大幅に低減できます。
被害の大半は風災由来ですから、「備えあれば憂いなし」の精神で早め早めの準備を心掛けましょう。専門家の知見や行政のマニュアルも参考に、自身のハウスに適した対策を講じてください。台風シーズンでも安心して栽培を続けられるよう、本ブログのポイントを活かして強いハウス作りに取り組んでいただければ幸いです。