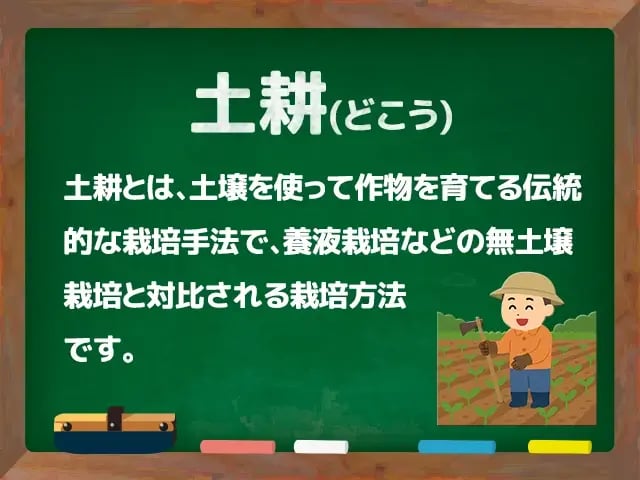
土耕とは、土壌を使って作物を育てる伝統的な栽培手法
土耕(どこう)とは、作物を育てる際に自然界に存在する土壌を培地として活用する伝統的かつ広範な栽培手法のことを指し、養液栽培や植物工場など、人工的に培養液を用いる無土壌栽培とは対極に位置します。 土耕では、土壌が単なる物理的な支えにとどまらず、水分、養分、空気、微生物環境など多くの要素を提供し、作物の健全な生育を支えます。
例えば、イチゴやトマト、レタスなど多くの野菜類が土耕で栽培されており、近年は高設土耕という方式も登場しています。 農業の現場では、土壌の肥沃度や保水性、排水性などを管理しつつ、肥料施用や病害虫防除などを行うことが重要です。 同意語としては「露地栽培」や「土壌栽培」などがあります。
土耕の概要
土耕は、古来から続く農業の基本形態であり、作物の根が土壌に直接張ることで、必要な養水分を吸収する仕組みです。 肥料や堆肥、石灰などを投入して土壌改良を行い、作物にとって適した環境を作る点が特徴です。 近年は土耕と養液栽培を比較する研究も盛んで、特に植物工場との比較で土耕の長所・短所が議論されています。
土耕の詳細説明
土耕では以下のような要素が密接に関わり合い、作物の成長に影響を与えます。
- 物理性
土壌の構造や粒径分布が根の張り方や水分の保持・排水性に影響します。 - 化学性
pH(ペーハー)、塩類濃度、養分含有量が作物の生育に直結します。 - 生物性
微生物群集の活性が、肥料成分の分解や病原菌抑制に重要です。
例えば、イチゴ栽培においては、養液栽培と比較して、土耕は果実の風味や糖度が良くなるとされ、いちご狩りなど観光農園でも人気です。 またトマト栽培では、土耕が土壌中の微生物バランスを保ちやすい点で有利とされます。 レタスのように短期間で収穫する葉物野菜も土耕で広く栽培されています。
土耕の役目または土耕の役割
土耕の役割は多岐にわたり、単なる作物栽培の手段を超えて、農業全体に以下のような貢献をしています。
- 土壌の多機能性活用
土は物理的支柱、養分供給、水分調節、病害抑制といった多様な機能を持ちます。 - コスト面の優位性
初期投資が比較的低く、小規模農家でも導入しやすい。 - 作物本来の風味向上
土壌特有の微生物環境や養分組成により、作物の風味や品質が向上する場合があります。
土耕の課題と対策
土耕には以下のような課題があり、それぞれに具体的な対策が模索されています。








