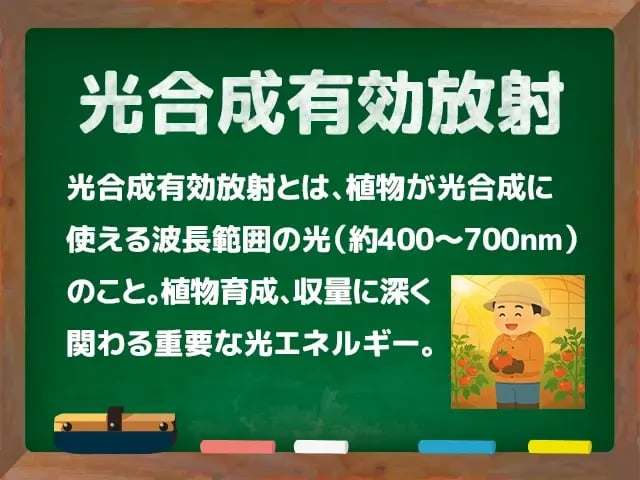
光合成有効放射(こうごうせいゆうこうほうしゃ)とは、植物が光合成に利用できる波長範囲の光で、おおむね400〜700ナノメートル(nm)に該当します。
この範囲の光は、太陽光全放射エネルギーの約45%を占め、植物の光合成速度を左右する重要なエネルギー源です。農業や園芸分野ではPAR(Photosynthetically Active Radiation)と呼ばれます。光合成有効放射は光量子束として表され、単位はμmol・m²・s⁻¹で示されます。
さらに、光飽和点や光補償点との関係を理解することは、作物ごとの最適環境を整える上で重要です。近年はLEDを用いた栽培や、過剰光対策として遮光ネットや遮光塗料(レディソルなど)が活用され、精密な光環境制御が進化しています。
同意語としては「PAR(ピーエーアール)」があります。
光合成有効放射の概要
光合成有効放射は、植物が光合成に使える可視光領域の光で、おおむね400〜700nmの波長が該当します。太陽光全体の約45%がこの領域に含まれ、植物が生育する上で極めて重要です。
PARは波長ごとに吸収効率が異なり、赤色光(620〜700nm)と青色光(450〜495nm)が特に光合成に効率よく利用されます。
過剰光による光障害を避けるため、施設栽培では遮光ネットや遮光塗料を用い、光環境を調節する技術が発展しています。
光合成有効放射の詳細説明
光合成は植物の生存に不可欠なプロセスであり、光合成有効放射はその基盤となるエネルギー源です。以下のポイントが重要です:
- 波長領域
光合成有効放射は400〜700nmの波長領域で、赤色光と青色光が最も光合成に寄与します。 - 光量子束
光合成有効放射は光量子束として表され、単位はμmol・m²・s⁻¹。光子(こうし)の数を計測し、光強度を評価します。 - 光飽和点と光補償点
植物は一定以上の光を受けると光合成速度が頭打ちとなり、これを光飽和点と呼びます。一方、光補償点とは、呼吸による二酸化炭素排出と光合成による吸収が均衡する光強度です。光飽和点以下で光量を調整することが、省エネ栽培や高品質生産につながります。 - LED活用
LEDの普及により、赤色光と青色光の比率を細かく制御できるようになり、作物の生育や収量を向上させています。
特に施設園芸では、過剰な太陽光が室温を上昇させ、光合成速度を低下させる問題が起こります。これを防ぐため、以下の方法が用いられます:
- 遮光ネット
遮光ネットは光量を調節し、光飽和点を超えない範囲に抑えると同時に室内温度を低下させます。 - 遮光塗料(例:レディソル)
遮光塗料はハウス外面に塗布し、赤外線を反射して熱侵入を防ぎながら、光合成有効放射は通す工夫がされています。
さらに、分光放射照度の測定やPPFD(Photosynthetic Photon Flux Density)管理によって精密な光環境が実現し、光合成速度の最大化を目指せます。
光合成有効放射の役割
光合成有効放射は、植物の光合成を支える最重要エネルギーであり、農業現場では以下の役割を果たします:
- 成長促進
光合成速度を高め、作物の生長を促進します。 - 収量安定
波長や強度を制御することで、収量や品質を安定化させます。 - 省エネ栽培
過剰光を遮ることで、冷房負荷を減らし、省エネにつながります。
光合成有効放射のメリットと課題
光合成有効放射の活用は多くのメリットをもたらしますが、課題も存在します。以下に主な課題と対策を挙げます。
課題1:測定機器の高コスト
光量子束計や分光放射照度計は高価で、小規模農家にとって導入が難しい場合があります。
対策:近年は安価な簡易機器やスマートフォン連動型センサーが登場し、導入障壁が低くなりつつあります。
課題2:作物ごとの光要求特性の違い
作物によって光飽和点・光補償点が異なるため、画一的な管理は難しく、調整が必要です。
対策:研究機関のデータや経験則を活用し、作物別の最適PPFD(Photosynthetic Photon Flux Density/光合成有効光量子束密度、ちょうどよい光の強さ)や波長比率を設定することが肝要です。
課題3:遮熱資材による光不足のリスク
遮光ネットや遮熱塗料は光を遮るため、過剰に使用すると光不足で生育が抑制されることがあります。
対策:遮光率を細かく選定し、LED補光を併用するなど、全体の光環境をトータルで管理することが重要です。








