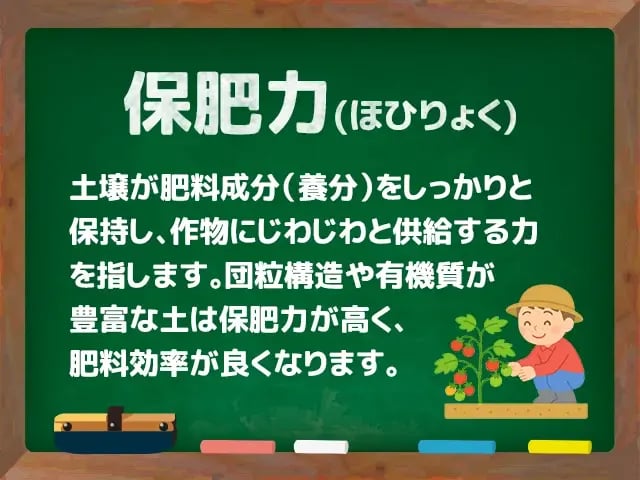
保肥力(ほひりょく)とは、土壌が肥料成分(養分)をしっかりと捕まえ、作物が必要なときに少しずつ供給できる能力を指します。
農業においては、作物の健全な成長や収量向上に直結する重要な土壌特性の一つです。保肥力が高い土壌では、肥料の流亡を防ぎ、効率的に養分を利用できるため、肥料代の節約にもつながります。
逆に、保肥力が低いと、施した肥料が雨などで流れてしまい、作物に必要な時に養分が不足するリスクがあります。
保肥力を高めるためには、腐植酸(ふしょくさん)を多く含む有機物の投入や、団粒構造(だんりゅうこうぞう)の形成促進が有効です。特に、バーミキュライトやゼオライトなどの改良資材も役立ちます。
同意語としては「肥料もち」や「養分保持力」などがあります。
保肥力の概要
保肥力とは、土壌が肥料成分を吸着し、植物が必要とするタイミングでじわじわと供給する性質のことを指します。
この力が高いと、肥料成分が一度に流れ出さず、作物が安定して栄養を受け取れるため、健全な生育を支えます。
主に腐植酸やフミン酸(ふみんさん)を豊富に含む土壌、有機質に富み団粒構造が発達した土壌で保肥力は高まります。バーミキュライトやゼオライトなどの天然改良資材の利用も、保肥力向上に効果的です。
保肥力の詳細説明
保肥力の基本的な仕組みは、土の粒子が持つ「陽イオン交換容量(よういおんこうかんようりょう:CEC)」によって説明されます。これは、土壌がカリウムやカルシウム、マグネシウムなどの養分イオンを吸着し、作物が吸収しやすい形で保持する力です。粘土質の土壌や、有機物に富んだ土壌はCECが高く、保肥力も優れています。
団粒構造の発達は、土の中に適度な隙間を作り、水分や空気の保持と同時に、養分の保持力も向上させます。この団粒構造を維持・促進するには、腐植酸やバーミキュライト、ゼオライトといった改良資材の投入が推奨されます。また、竹炭などの天然資材も保肥力向上に効果を発揮することが知られています。
保肥力の役目または保肥力のメリットと課題
メリット1:肥料効率が向上する保肥力が高い土壌では、施した肥料成分が流出しにくく、必要な時に必要な量だけ植物が吸収できるため、肥料の無駄遣いが減り、経済的にも環境的にも効果的です。
メリット2:作物の生育が安定する
肥料成分が土壌にしっかりと保持されることで、作物は成長に必要な栄養を途切れることなく吸収でき、病害虫への抵抗力も高まるといわれています。
課題と対策1:砂地では保肥力が低い
砂質土壌ではCECが低く、養分が流亡しやすい課題があります。対策として、腐植酸やバーミキュライト、ゼオライトを施用し、有機物量を増やして保肥力を高めます。
課題と対策2:有機物不足による保肥力低下
連作や過剰耕起によって土壌有機物が減少すると、保肥力が低下します。対策として、堆肥や緑肥作物(クローバーやソルゴーなど)を活用して土壌改良を行います。
課題と対策3:過剰施肥による塩害リスク
保肥力を過信して肥料を多く施すと、土壌中の塩分濃度が高まり、塩害の原因となることがあります。対策として、土壌診断を定期的に行い、適切な施肥設計を心がけます。








