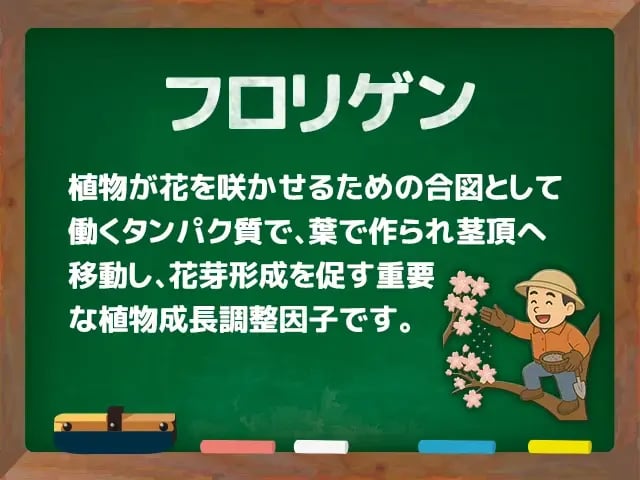
フロリゲン(ふろりげん)とは、植物が花を咲かせる時期を決める重要な「花咲かホルモン」として知られる植物由来のタンパク質であり、光や気温などの環境情報を感知した葉で合成され、茎頂(けいちょう)にある分裂組織へと移動して花芽(はなめ)形成を誘導します。
2007年に日本の研究者らによりその正体がFT(FLOWERING LOCUS T)あるいはHd3aタンパク質であると特定され、長年「幻のホルモン」と呼ばれてきた謎が解明されました。
このメカニズムの理解は、作物の開花制御や品種改良、バイオマス利用など、現代農業においても応用が広がっています。
同意語としては「花成ホルモン」「ホルモンフロリゲン」などがあります。
フロリゲンの詳細説明
フロリゲンは、1936年にソビエト連邦の植物生理学者チャイラヒャンによって仮説として提唱されましたが、その正体は長らく不明でした。
葉にある光受容体(ひかりじゅようたい)が日長(昼の長さ)を感知し、フィトクロム(光の質を感知するタンパク質)が遠赤色光などの刺激に応じて、フロリゲン合成に関わる遺伝子を活性化します。短日植物では日が短くなると、長日植物では日が長くなると、フロリゲンの発現が促進されるため、植物種ごとに光条件への応答が異なります。
合成されたフロリゲンは維管束(いかんそく)の篩管(しかん)を通って茎頂に運ばれ、そこで14-3-3タンパク質およびFDタンパク質(転写因子)と結合し、フロリゲン活性化複合体を形成します。この複合体が核に移行し、花芽形成に関与する遺伝子群の転写を活性化させ、開花のプロセスが始まります。
特筆すべきは、フロリゲンは開花のみならず、イモ類における塊茎(かいけい)形成など、植物の器官形成にも影響を及ぼす多機能性を持つ点です。また、フロリゲンの合成・移動・作用の全体像は現在も精力的に研究されており、リン酸化などの後成的修飾(こうせいてきしゅうしょく)も活性調整に関与していると考えられています。
フロリゲンは英語で florigen といいます。同じく、「花成ホルモン(花を咲かせるホルモン)」とも呼ばれることがあり、英語では次のようにも表現されます。
- flowering hormone(花成ホルモン)
- floral stimulus(開花刺激)
- flower-inducing protein(開花誘導タンパク質)
ただし、正式な学術用語や研究論文などでは florigen が一般的に使われています。
フロリゲンの役割
- 開花時期の調整
光周期や気温に応じて開花時期を正確に制御し、受粉や収穫の効率化に貢献します。 - 器官形成の誘導
- イモ類の塊茎や果実の発育にも関与しており、フロリゲンは単なる開花因子にとどまらない重要な調整因子です。
- 品種育成への応用
- 開花を早める・遅らせる制御技術により、地域適応型品種の開発や二期作対応などが可能になります。
フロリゲンに関する課題とその対策
1. 環境変動による発現不安定
異常気象や温暖化により、植物が期待する日長や温度条件と実際の環境が合わない場合、フロリゲンの発現タイミングがずれ、開花不良を引き起こす可能性があります。
対策:気候変動に強い遺伝子組換え品種の導入や、人工光源による補光栽培で開花制御を補う技術が開発されています。
2. 作物間での作用の差異
フロリゲンの受容や転写因子との相互作用は作物種により異なるため、汎用的な技術応用が難しい場合があります。
対策:作物ごとのフロリゲン関連遺伝子を特定し、個別の育種プログラムで適正な遺伝子発現を促す設計が必要です。
3. 移動経路の遮断リスク
葉から茎頂までの輸送経路(篩管)が老化や障害で損なわれると、フロリゲンが正しく到達せず、開花異常につながります。
対策:植物の栄養状態を適切に管理し、病害虫防除や剪定(せんてい)で健全な輸送経路を確保することが重要です。








