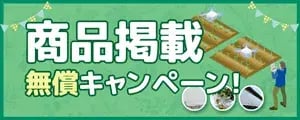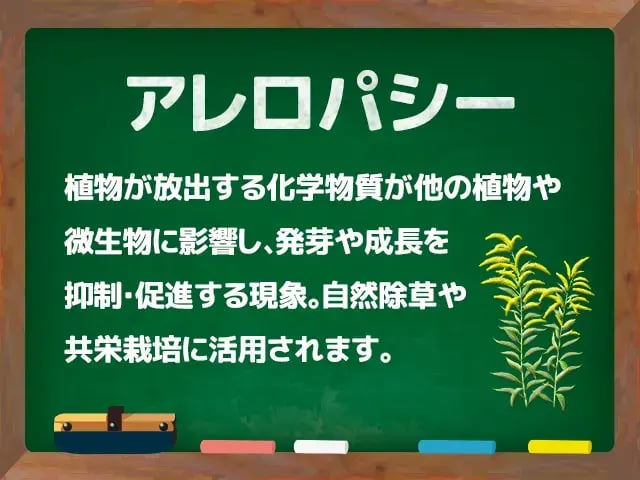
アレロパシー(あれろぱしー)とは、植物が根や葉から放出する化学物質によって、他の植物や微生物、害虫などの発芽や成長を抑制・促進する現象です。
農薬に頼らず雑草を抑える「自然除草」や、コンパニオンプランツ栽培などで活用される栽培手法として注目されています。
アレロパシー(あれろぱしー)とは、植物が自らの根や葉、茎、果実、残渣(ざんさ)などから化学物質を放出し、それが周囲の植物や微生物、昆虫に影響を及ぼす現象です。
これらの化学物質はアレロケミカル(Allelochemical)と呼ばれ、自然界における植物同士の「化学的コミュニケーション」の一形態です。
アレロパシーは、植物が競合を避け、自らの生育環境を有利に保つための防衛メカニズムとして発達してきました。農業分野では、これを雑草防除や病害虫抑制に応用することで、農薬使用を減らす持続可能な技術として期待されています。
アレロパシー効果を活かす栽培手法には、カバークロップ(覆い作物)やグランドカバー植物の導入、残渣還元法、輪作設計などがあります。 また、「ロケミカル(Allelochemical)」や「生物化学相互作用」という言葉でも説明されることがあり、環境調和型農業の研究分野で特に注目されています。
同意語としては「他感作用(たかんさよう)」があります。
アレロパシーの概要
アレロパシーは、植物が分泌する化学物質によって他の植物の生育に影響を与える生理的作用を指します。
これらの物質は主に根分泌液・落葉の分解物・揮発性成分などとして環境中に放出されます。植物同士の競争を制御する自然現象であり、「強い植物」が自らの生育スペースを守るために働かせる仕組みです。
農業では、アレロパシー活性を持つ植物をうまく利用することで、雑草の発芽を抑制したり、病害虫の活動を抑えたりすることが可能になります。たとえば、セイタカアワダチソウやナガミヒナゲシ、ミント、ローズマリーなどが強いアレロパシー効果を持つ代表的な植物として知られています。
アレロパシーの詳細説明
アレロパシー作用は、発芽阻害・生育抑制・病害虫制御など多面的なメカニズムを通して現れます。以下にその代表的な作用を挙げます。
- ① 発芽抑制作用
アレロケミカルが土壌中に拡散し、他の植物の種子の発芽シグナルを阻害します。これにより、雑草の発生が自然に抑制されます。 - ② 成長抑制作用
化学物質が根や葉の細胞分裂を阻害し、根毛の形成や栄養吸収を妨げます。特に「サンドイッチ法(サンドイッチほう)」と呼ばれる実験法でその効果が確認されています。 - ③ 微生物や害虫への作用
- アレロケミカルが土壌微生物や昆虫にも影響を与え、特定の病原菌や害虫の活動を抑制します。たとえば、ヘアリーベッチ(Hairy Vetch)のアレロパシー成分は線虫や雑草を抑える効果が報告されています。
アレロパシーを利用することで、農薬の使用を抑えつつ雑草や害虫を制御できるため、有機農業・自然農法・持続的栽培における重要な要素とされています。近年では、コンパニオンプランツ(共栄植物)として異種植物を組み合わせる手法にも応用されています。例えば、トマトとバジル、キャベツとミントの組み合わせなどが有名で、互いのアレロパシー効果を利用して害虫を寄せ付けにくくします。
アレロパシーの役割とメリット
- 雑草抑制と農薬削減
アレロパシー植物を利用することで、除草剤の使用量を大幅に削減できます。これにより環境負荷が軽減され、農地生態系の保全に寄与します。 - 生態系バランスの維持
アレロケミカルの働きにより特定種の過剰繁茂を抑え、多様な植物種が共存できる環境を作ります。これが土壌動物や微生物の生態系維持にもつながります。 - 病害虫防除効果
ミントやローズマリーなどの植物から発せられる芳香成分には防虫効果があり、ハーブを利用した生物的防除の基盤となっています。

緑肥に用いられるヘアリーベッチ(ナヨクサフジ・弱草藤)
アレロパシーの課題と対策
- 課題1:次作作物への悪影響
アレロパシー活性が強い植物の残渣(ざんさ)をそのまま土壌に鋤き込むと、次作の発芽や根の成長が阻害される場合があります。
対策:残渣を堆肥化して分解を進め、アレロケミカルを無害化した上で使用します。輪作体系を工夫し、相性の良い作物(例:ヘアリーベッチ後のトウモロコシなど)を選定します。 - 課題2:環境条件による効果変動
アレロパシー効果は気温、湿度、土壌p、微生物活性などに影響されやすく、常に一定の効果を得るのが難しいという問題があります。
対策:圃場(ほじょう)の土壌環境を安定させ、灌水管理や有機物補給により微生物バランスを保ち、効果を安定化させます。 - 課題3:有効物質の特定と応用の限界
アレロケミカルの種類は多岐にわたるため、すべての植物で効果を予測することは困難です。過剰な効果は有用作物に害を与える可能性もあります。
対策:大学・研究機関のデータを参考に、効果が確認された植物(ヘアリーベッチ、クロタラリアなど)を選定し、少量の試験区で効果を検証してから本圃場に導入することが推奨されます。
アレロパシーの応用事例
- ヘアリーベッチを冬期カバークロップとして導入し、春の雑草発生を抑制。
- ローズマリーを果樹園の周囲に植えて、害虫の侵入を防止。
- ミントを野菜畑の区画ごとに配置し、病害虫の発生を軽減。
- セイタカアワダチソウやナガミヒナゲシなどのアレロパシー強植物を観察対象として教育現場で利用。
参照
- JAあつぎ:「アレロパシー『他感作用』について | 営農通信」
https://www.ja-atsugi.or.jp/member/einou/2025/06.html
→ 被覆植物としてのヘアリーベッチの例と「除草剤使用量の削減に有効」という記述あり。 - 農業環境技術研究所(NARO):「アレロパシー研究の最前線(藤井義晴)」PDF資料
https://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/inovlec2004/1-3.pdf
※アレロパシーの定義・作用経路・農業上の意義などが整理されています。 - 農林水産省:「緑肥作物の利用 土壌を肥沃化する目的で栽培され …」PDF資料
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti28.pdf
※緑肥作物による雑草抑制およびアレロパシー作用(他感作用)について言及があります。 - 生物系特定産業技術研究支援センター(BRAIN):研究課題「アレロケミカルの探索と新規生理活性物質の開発」説明ページ
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/inv_up/theme/2008/023742.html
※アレロケミカル(他感物質)を農業利用する研究を公的に採択している事例です。