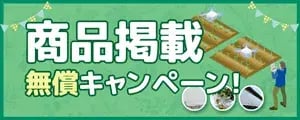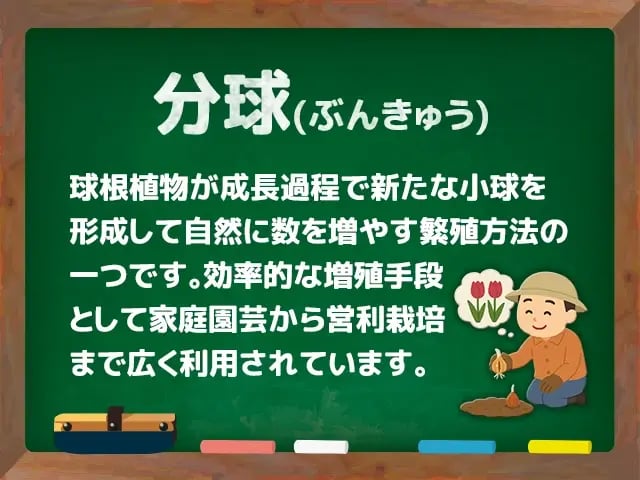
分球(ぶんきゅう)とは、球根植物が成長する過程で、親球(しんきゅう)の周囲に自然に形成される子球(しきゅう)によって個体数を増やす繁殖法です。主に地下部にできる肥大した器官(球根)を通じて増殖するため、種子繁殖に比べて遺伝的なばらつきが少なく、確実な品質保持が可能です。
この方法は多年性の草花や一部野菜類などで広く見られ、農業の現場でも繁殖効率を高める手法として重宝されています。
同意語としては「球根増殖」「自然分球」「栄養繁殖」などがあります。
分球の概要
- 分球とは
球根植物が親球から子球を形成して自然増殖する栄養繁殖の一種。 - 対象作物
主にチューリップ、タマネギ、ダリア、ムスカリ、ニンニクなど。 - 発生部位
鱗茎(りんけい)や塊茎(かいけい)の基部・芽の周囲などで形成される。
分球の詳細説明
分球は、球根を持つ植物が自己の遺伝情報を保ったまま新たな個体を生み出す方法として、特に種子による繁殖が難しい品種や、開花に数年かかる植物において非常に有効です。
たとえばチューリップでは、親球の基部にできた子球原基(しきゅうげんき)が徐々に肥大化して独立球根となります。またグラジオラスなどでは、発芽した芽の基部が膨らみ、数珠状に子球が形成される例もあります。このような形で分球は植物によって多様な様相を持つため、品種特性を把握したうえでの適切な管理が必要です。
農業現場では、植え替えの際に親球と子球を丁寧に分離して育苗資材として再利用することが一般的です。 営利栽培では、球根掘り上げ後の乾燥や選別作業とセットで行われ、健全な子球を翌年の栽培に用いることで、病害リスクの低減と生産効率の向上が図れます。
特にタマネギやニンニクでは、規模の大きな分球繁殖が導入され、種子更新よりも実用的とされます。
分球の役割・メリット
- 品質の安定
- 親と同じ遺伝的特徴を持つため、均質な作物が得られやすい。
- 繁殖の容易さ
発芽率に左右されず、高確率で生育が可能。 - 栽培の計画性
次年度以降の作付け計画に応じた数の球根を確保できる。
分球に関する課題とその対策
1. 病気の伝播
親球がウイルスや糸状菌に感染していると、子球にも病害がそのまま伝わる可能性があります。
対策:収穫後の球根を十分に乾燥させ、傷や腐敗部の有無を確認し、消毒処理や健全株の選抜を徹底することが重要です。
2. 子球の成長不良
栄養不足や過密栽培により、子球が小さくなったり、十分に成熟しないことがあります。
対策:親球の植え付け間隔を適切に保ち、十分な日照・肥培管理を行うことで健全な子球育成を促進します。
3. 作業手間の増加
収穫後の球根掘り上げ、乾燥、選別、貯蔵など、工程が多く労力がかかります。
対策:選別機や乾燥機を活用した機械化導入や、家庭園芸では簡便なネット乾燥などで省力化を図ります。