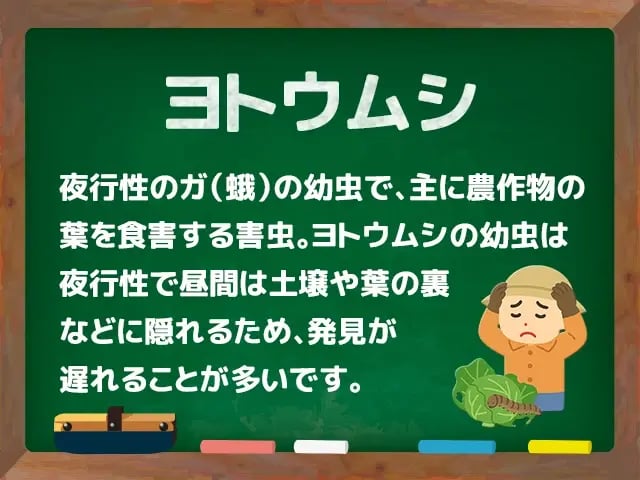
ヨトウムシの概要
ヨトウムシ(よとうむし)とは、チョウ目ヤガ科に属する蛾の幼虫であり、主にキャベツ、トマト、ピーマンなどの野菜類に被害を及ぼす代表的な農業害虫です。
ヨトウムシは夜行性で、昼間は葉の裏や土の中に隠れて活動を停止し、夜間に出てきて植物の葉や茎を食害します。
特に幼虫が小さいうちは農薬が有効ですが、成長すると薬剤の効果が著しく低下し、物理的な除去が必要になります。
5~6月と9~10月に発生のピークを迎えることが多く、これに合わせた計画的な防除が重要です。
同意語としては「ヨトウガ幼虫」「夜盗虫(やとうむし・よとうむし)」などが使われます。
ヨトウムシの詳細説明
ヨトウムシの成虫は15~20mmの体長で、灰褐色または黒褐色をしており、夜間に活発に活動します。卵は葉の裏に数十~数百個まとめて産み付けられ、孵化した幼虫は一斉に葉を食べ始めます。特に若苗期には葉が丸坊主になるほど激しく食害されることもあります。成長した幼虫は大きくなりながら葉、茎、さらには果実部にも食害を及ぼします。
また、ヨトウムシは種類も豊富で、特に農業現場で問題となるのは以下の3種です。
成虫は春(4~5月)と秋(9~10月)に多く見られ、年2回の発生ピークがあります。蛹(さなぎ)で冬を越し、4月頃から羽化し始めます。葉裏に卵を産み付け、夜間に活動し、日中は土中や葉陰に隠れる性質があります。このため被害の発見が遅れやすく、防除が難しい害虫とされています。
ヨトウムシの課題と対策
課題①:成長後の薬剤耐性と結球内侵入
ヨトウムシの幼虫は成長するにつれて薬剤への耐性が高まり、特にキャベツやハクサイのような結球野菜の内部に潜り込んだ場合、薬剤が届かず駆除が困難になります。
対処方法:
-
定植前に粒剤(オルトランなど)を土壌に施用し、初期の食害を抑える。
-
初期成長期には葉裏の点検と手作業による捕殺を併用する。
-
幼虫期の脱皮を阻害する昆虫成長制御剤(IGR剤)の活用も効果的。
代表例としてカスケード乳剤(有効成分:フルフェノクスロン)があり、これはキチン質合成阻害作用によって幼虫の脱皮を妨げ、成長を止めて死滅させる。
特に幼虫が若齢の段階で散布することで高い防除効果が得られ、天敵やミツバチへの影響が比較的少ないため、IPM(総合的害虫管理)体系にも組み込みやすい。 -
ただし、カスケード乳剤は幼虫期に特化した作用であり、成虫や蛹には効果が乏しいため、他剤(BT剤やスピノサド剤など)とローテーション散布することが望ましい。
課題②:夜間活動・昼間の隠蔽性
夜行性であるため日中には発見しづらく、見逃されやすい。土中や葉裏に隠れているため、発見が遅れると被害が拡大しやすい。
対処方法
- 早朝や夕方の観察を強化し、葉裏を重点的に確認。
- 定期的に土壌を耕し、越冬する蛹の除去も有効。
- 発生初期を捉えるためにフェロモントラップやライトトラップを併用する。
課題③:爆発的な繁殖力
一度に産み付ける卵の数が数百個にのぼるため、発見が遅れると短期間で個体数が爆発的に増加し、被害が急速に広がる恐れがあります。
対処方法- 防虫ネットや寒冷紗の設置により成虫の飛来と産卵を物理的に阻止。
- 捕殺および米ぬかトラップ等を併用して成虫・幼虫の発生源を抑える。
- カスケード乳剤のような残効性のあるIGR剤を若齢幼虫の時期に散布し、次世代の個体増加を抑制する。
薬剤を使わない防除法
- 米ぬかトラップ
容器に米ぬかを入れて株元に設置し、夜間活動中の幼虫を誘引して捕獲。 - 草木灰の散布
忌避効果とともに土壌改良、追肥効果も期待できる。 - 防虫ネット・寒冷紗
物理的な飛来防止で産卵自体を抑える。 - マリーゴールド・ミントの混植
忌避植物として利用可能。
天敵の利用
ヨトウムシには自然界に天敵が多数存在します。特に以下が知られています。
- 鳥類
ヒヨドリ、スズメなど。 - カエル類
トノサマガエルなど。 - ムカデやクモ類
夜間に活動し、幼虫を捕食。
対象作物と影響
ヨトウムシは極めて多食性で、以下の作物に被害を与えることが確認されています。
- キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ナス、ピーマン(野菜類)
- トウモロコシ(穀物類)
- トマト、バジル、ネギ、大根(野菜類)
- ジャガイモ、玉ねぎ(野菜類)
まとめ:早期発見・多角的防除が鍵
ヨトウムシによる農作物への被害を最小限に抑えるためには、以下のような多角的なアプローチが重要です。
- 定植前の土壌処理(粒剤の施用)
- 日常的な葉裏の観察と物理的捕殺
- 防虫ネットや混植などの忌避戦略
- 米ぬかトラップなどの環境負荷の低い捕獲法
- 幼虫期を狙ったカスケード乳剤などIGR系薬剤の適切な使用
これらを組み合わせることで、薬剤への過度な依存を避けつつ、天敵保護と持続可能な害虫管理を両立することが可能です。カスケード乳剤のような選択的薬剤をIPM体系に取り入れることで、環境と生産のバランスを保ちながら、長期的に安定した防除効果を得ることができます。








