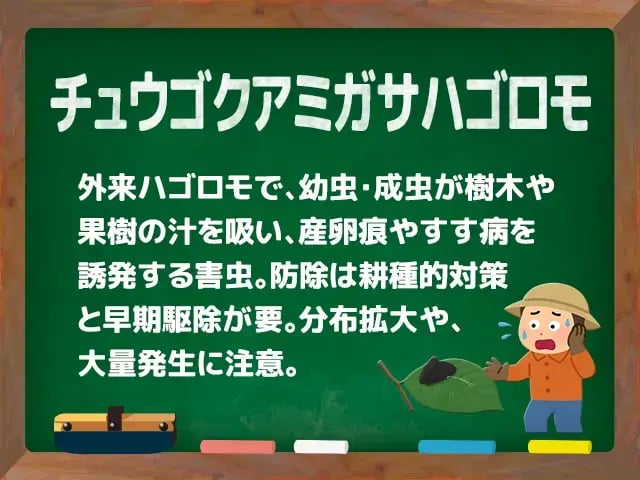
チュウゴクアミガサハゴロモは外来種の害虫。分布拡大や大量発生に注意。
チュウゴクアミガサハゴロモ(ちゅうごくあみがさはごろぐも)とは、東アジア由来の外来種のハゴロモ科昆虫で、都市の街路樹や庭木、果樹園など多様な植栽で確認されています。
成虫・幼虫が植物の師管から樹液を吸汁し、排泄物が葉面に付着してすす病の媒介条件をつくり、樹勢低下や品質劣化を招きます。産卵時には枝に傷をつけて産卵痕を残し、枝折れや枯れ込みの原因にもなります。
近年は東京や茨城など関東圏を含む各地で分布が拡大し、都市緑化樹から果樹園まで被害の波及が問題化しています。耕種的対策(剪定・清掃・物理的除去)を基盤に、発生状況を常時モニタリングし、幼虫・成虫段階での迅速な駆除を繰り返すIPM(アイピーエム)が有効です。
同意語としてはアミガサハゴロモ、ハゴロモ外来種 などがあります。
チュウゴクアミガサハゴロモの概要
- 分類
カメムシ目(半翅目)・ハゴロモ科。蛾に似るが翅(はね)に鱗粉はありません。 - 外観
体長約1.0~1.5cm。茶褐色~さび色の翅に三角形の白斑。幼虫は白い蝋物質(ろうぶっしつ)をまとい綿状に見えることがあります。 - 生活史
樹木の樹液を幼虫・成虫ともに吸汁。初夏~秋に活動が活発で、枝に産卵して白い産卵痕を形成します。 - 被害症状
吸汁による樹勢低下、枝の傷・折損、排泄物が誘発するすす病で葉が黒変し光合成が阻害。 - 宿主範囲(広食性)
ブルーベリー、ブドウ、ナシ、オリーブ、チャ、カキ、カエデ、ケヤキ、サクラ類など多数。
.webp?width=640&height=480&name=%E8%91%89%E3%81%AB%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%83%8F%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%83%A2(%E5%A4%96%E6%9D%A5%E7%A8%AE).webp) 葉に止まるチュウゴクアミガサハゴロモ(外来種)
葉に止まるチュウゴクアミガサハゴロモ(外来種)
チュウゴクアミガサハゴロモの詳細説明
- 生態と分布
都市公園・沿道・住宅地の庭木から果樹園へと分布を広げやすく、温暖域での越冬が示唆されています。緑陰樹や生け垣で大量発生すると、近隣の果樹に飛来・定着するリスクが増します。 - 加害の仕組み
口針で師管から糖分の多い樹液を吸い、その排泄物として糖分を多く含む蜜露(みつろ)を排出します。葉面の蜜露はすす病菌の基盤となり、葉色の黒変・黄化・落葉を誘発します。さらに産卵時に枝皮を切り裂いて卵を産み付けるため、細枝の産卵痕が連なり、折れや枯れ込みの起点になります。 - 見分け方(アミガサハゴロモ違い)
在来のアミガサハゴロモと混同されがちです。翅の色調、白斑の形、発生場所・時期、幼虫の蝋質の量感などを複合的に確認してください。誤認は駆除のタイミングを遅らせる要因になります。 - 被害作物と影響
園芸作物では糖度・着色・外観の低下、収穫・選果時の作業性悪化を招きます。庭木・街路樹では美観と健全性が損なわれ、落葉・枝枯れが発生します。
課題と対策
- 課題1:すす病の多発と品質劣化
蜜露の堆積で葉面・果面が黒変し、光合成と着色が阻害されます。果樹では外観・糖度への悪影響が顕著です。
対策:発生初期から葉裏・枝分かれ部を重点的に点検し、幼虫・成虫を物理的に駆除。被害葉・果は適宜除去し、樹冠内の風通しを改善。収穫後は葉面洗浄や雨当たりの確保で蜜露残渣を減らします。 - 課題2:産卵痕による枝折れ・枯れ込み
連続した産卵痕が細枝を脆くし、風雨で折損や枯れ上がりが生じます。翌季の結実量低下にもつながります。
対策:冬~早春の病害虫防除作業として、産卵痕のある枝を剪定し、袋詰め密閉→可燃ごみ等で処分。圃場外への持ち出し・放置は分布拡大の要因となるため厳禁。 - 課題3:都市部から園地への再侵入(分布拡大)
公園・街路樹での大量発生が近隣園地への継続的な侵入源になります。単独園地での対策だけでは限界があります。
対策:自治体・地域住民・生産者の協働で定期的な一斉点検・除去を実施。黄色粘着板やライトトラップなどで発生把握を行い、ピーク前に駆除を集中。樹冠下の落葉・枝条を清掃し、雑草過繁茂を避けて越冬・潜伏場所を減らします。
チュウゴクアミガサハゴロモ駆除方法の要点
- モニタリング
発生期は週1回以上の巡回。葉裏・樹皮の割れ目・枝の分岐部を重点確認。 - 物理的除去
小規模は手取り・捕虫網、幼虫の群れは刷毛や水流で払い落として袋詰め廃棄。 - 剪定と衛生
産卵痕枝は切除し密閉処分。剪定器具はアルコールで都度消毒。 - 環境管理
樹冠内の透光・通風を確保し、潅木の混み合いを解消。灌水・施肥は樹勢を回復させる範囲で適正化。 - 地域連携
東京・茨城など都市近郊では、公園・街区と果樹園の協調管理が再侵入防止に不可欠。
よくある質問(FAQ)
Q:アミガサハゴロモとの違いは?
A:翅の白斑形状、幼虫の蝋質の量、発生環境の違いなどを総合判断します。写真記録を残し、同定に迷う場合は地域の普及指導機関に相談してください。
.webp?width=640&height=480&name=%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%83%8F%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%81%AE%E6%88%90%E8%99%AB(%E5%9C%A8%E6%9D%A5%E7%A8%AE).webp) アミガサハゴロモの成虫(在来種)
アミガサハゴロモの成虫(在来種)
| 観点 | チュウゴクアミガサハゴロモ | アミガサハゴロモ | 現場メモ |
|---|---|---|---|
| 来歴 | 外来種(近年拡大) | 在来種 | 外来情報が出ている地域は要注意。 |
| 翅の模様 | 茶〜さび色で三角形の白斑が明瞭 | 淡色〜灰褐色で網目状斑、白斑目立たず | まずは翅の白斑の有無・形を確認。 |
| 体サイズ感 | やや大きめ(約1.0–1.5 cm)でがっしり | やや小さめで繊細 | 並べて見ると差が出やすい。 |
| 体色の印象 | 全体に濃色 | 全体に淡色 | 写真記録で比較しやすい。 |
| 幼虫の見え方 | 白い蝋質が多く綿毛状の群れを作りやすい | 蝋質は出るが相対的に控えめ | 幼虫群れの“モワッ”と感が判断材料。 |
| 産卵痕 | 連続・深めで枝折れや枯れ込み起点に | 痕は残るが連続性・深さは弱め | 枝先の列状痕を要チェック。 |
| 被害の傾向 | 蜜露→すす病、果樹・庭木で苦情・被害大 | 被害は出るが相対的に軽い | 収穫物の見栄え・糖度低下に注意。 |
| 発生場所傾向 | 都市公園・街路樹→果樹園へ拡大しやすい | 各環境で見られるが爆発的侵入は少なめ | 都市近郊圃場は監視頻度を上げる。 |
| 主な宿主例 | ブルーベリー、ブドウ、ナシ、オリーブ、チャ等 | 広く樹木類 | 圃場周辺の庭木も含めて点検。 |
| 同定のコツ | 三角白斑+濃色+綿毛状幼虫+深い産卵痕 | 網目模様+淡色+蝋少なめ | 3点(翅・幼虫・産卵痕)をセットで判定。 |
A:登録状況は地域・作物で変動します。まずは耕種的防除(剪定・物理的駆除・衛生管理)を基盤にし、必要に応じて地域の最新情報に従ってください。
Q:家庭の庭木でも対処できますか?
A:できます。幼虫期に重点を置き、群れを見つけ次第の物理的除去と、枝先の産卵痕切除・密閉廃棄を徹底してください。
Q:蜜露は人間が食べても大丈夫?
A:蜜露は「虫の排泄物で高糖分ゆえ細菌・カビが繁殖しやすい」「農薬・土埃・花粉の付着リスク」「カビ・昆虫由来成分でアレルギーの恐れ」があるため、食用はおすすめしません。
参照
- 群馬県(病害虫発生予察 特殊報):「令和6年度 病害虫発生予察特殊報 第2号(チュウゴクアミガサハゴロモ)」
https://www.pref.gunma.jp/page/689254.html
→ ナシほ場のトラップで成虫を確認し、農林水産省・横浜植物防疫所で同定。県内初確認の経緯、学名、発生植物、発生概況と対応が整理。 - 神奈川県(農業技術センター):「令和6年度 病害虫発生予察特殊報(第1号)チュウゴクアミガサハゴロモ」PDF
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/108747/20240814tokusyuhou.pdf
→ 形態・生態、被害症状、寄主例、横浜植物防疫所での同定を明記。剪定・処分など耕種的防除の要点も記載。 - 千葉県(農林総合研究センター等):「チュウゴクアミガサハゴロモの確認について」PDF
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/documents/20250716tokushuhou01.pdf
→ 県内確認の状況、寄主、被害リスク、登録薬剤がないため耕種的・物理的防除を推奨などを整理。 - 埼玉県 病害虫防除所:「令和7年度 病害虫発生予察注意報 第8号(植木類・チャ・果樹類・宿根アスター等)」
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/chuiho-r7-8.html
→ 県内全域で多発のおそれを警戒。誘殺数の増加、寄主範囲(80種以上)、果樹への影響と注意点を公表。PDF原本も掲載。 - 環境省・生物多様性センター(いきものログ):「チュウゴクアミガサハゴロモ(学名:Ricania shantungensis)観察記録」
https://ikilog.biodic.go.jp/LifeSearch/detail/?life_darwincore_id=13339096
→ 公的市民科学データベースでの国内出現記録。和名・学名・出現地点などの基礎情報を参照可能。 - 農林水産省(植物防疫関係):「病害虫発生予報(全国)/重要病害虫の連絡先案内」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_yoho/attach/pdf/index-72.pdf / 横浜植物防疫所(病害虫同定・診断)
→ 不審な被害発生時は植物防疫所・各県防除所へ通報する手順と連絡先。横浜植物防疫所には病害虫同定診断担当の連絡先が掲載。 - 日本植物園協会(公的法人):「外来種チュウゴクアミガサハゴロモ」PDF(園芸・樹木管理向け注意喚起)
https://jabg.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/チュウゴクアミガサハゴロモ.pdf
→ 国内外での分布拡大、発生期、被害(すす病・枝損傷)と寄主例を図表で解説。自治体・施設の現場対応の参考資料。








