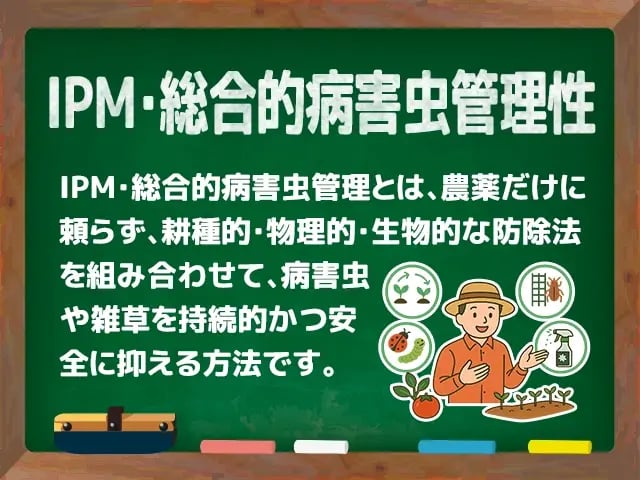
IPM・総合的病害虫管理(あいぴーえむ・そうごうてきびょうがいちゅうかんり)とは、Integrated Pest Managementの略で、病害虫や雑草といった有害生物(ゆうがいせいぶつ)の発生を防ぐために、農薬だけに依存せず、耕種的防除(こうしゅてきぼうじょ)、物理的防除(ぶつりてきぼうじょ)、生物的防除(せいぶつてきぼうじょ)など様々な手法を組み合わせて行う総合的な防除体系です。
農林水産省もIPMの普及に取り組み、IPMマニュアルや資材カタログの整備を通じて、持続可能な農業の実現を支援しています。
同意語としては「統合的防除」「総合防除」がよく使われます。
IPM・総合的病害虫管理の概要
IPMは、作物の健康を保ちながら、環境負荷を減らし、経済的にも無理のない方法で病害虫の発生を抑える考え方です。
単一の方法に偏ることなく、以下のような複数のアプローチを柔軟に組み合わせることが特徴です。
IPM・総合的病害虫管理の詳細説明
IPMは「病害虫雑草」を対象とし、それらの発生予測と被害評価をもとに、どの手段をどのタイミングで使うかを計画的に判断する必要があります。たとえば害虫の発生をフェロモントラップで監視し、ある基準を超えた場合にのみ農薬を使用する、といった使い方がされます。
このような判断には観察・記録・分析が必要であり、学術会議や現場での経験の蓄積が活かされます。
また、生物的防除では「天敵」の保護や導入が重要であり、これにより生態系のバランスを保ちながら、持続的な防除が可能となります。特に、ハウス栽培や施設園芸においては天敵の管理がIPMの要になります。
IPM・総合的病害虫管理の役割
- 農薬使用量の削減:環境と人への影響を減らす。
- 薬剤抵抗性の発達抑制:多様な防除手段で害虫の適応を防ぐ。
- 安全な農産物の供給:農薬残留を抑え、消費者の安心を確保。
IPM・総合的病害虫管理の課題と対策
1. 実施の複雑さ
複数の防除法を併用するため、知識や判断力が求められます。
対策:農業普及センターや地域農協の支援を活用し、段階的に導入するのが有効です。IPMマニュアルなどの活用も推奨されます。
2. 生物防除の不確実性
天敵や微生物の効果が気象や栽培環境により変動しやすく、安定性に欠ける場合があります。
対策:害虫の発生を定期的にモニタリングし、状況に応じた他手段(物理的・化学的)を準備しておくことが重要です。
3. 経済的負担と労力
資材費や人手がかかるため、導入初期には負担感があります。
対策:国や自治体の補助金制度、資材カタログによる適正価格資材の選定を活用しましょう。地域全体で導入すればコストを抑えられる場合もあります。








