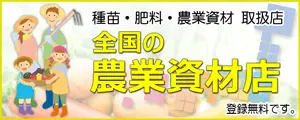タマネギべと病(たまねぎべとびょう)の概要
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)とは、卵菌(らんきん)類(糸状菌(しじょうきん)とは別系統)の病原体が主に葉の気孔(きこう)から侵入し、葉に感染して起こる感染性病害です。肥料不足、乾燥、水切れ、寒害などの生理障害ではありません。また、葉が黄化(おうか)する見た目だけで決め打ちできる病気ではなく、葉裏(はうら)の病徴(びょうちょう)確認と、夜露や過湿など発生条件との整合で判断します。
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)の詳細説明
病原は主にPeronospora destructorで、糸状菌(しじょうきん)とは系統の異なる卵菌(らんきん)類に属します。葉の気孔(きこう)などから侵入して葉内で増殖し、条件がそろうと葉裏に分生胞子(ぶんせいほうし)(胞子状の繁殖体)を形成します。乾いた葉面では感染が成立しにくく、葉が長時間ぬれる条件(夜露(よつゆ)、霧、降雨、過湿)が発病成立の前提条件になります。
初期症状は葉に淡い退色(たいしょく)や不明瞭(ふめいりょう)な斑(ふ)が現れる程度で見落とされやすく、進行すると葉の黄化(おうか)、湾曲(わんきょく)、倒伏(とうふく)が増えます。本病の重要な識別点は、湿度が高い朝方などに葉裏へ灰紫色(はいいろむらさきいろ)〜暗灰色のかび状病徴が現れやすいことで、乾燥すると視認しにくくなります。窒素欠乏や根傷みなどの生理障害、紫斑病(しはんびょう)や灰色かび病(はいいろかびびょう)とは、病斑の質、葉裏の所見、圃場内での広がり方が異なります。
被害の本質は、健全な葉が失われることで光合成(こうごうせい)量が減少し、肥大期に必要な同化産物が確保できなくなる点にあります。葉の枯死が早く進むほど回復は困難となり、結果として肥大不足、玉(たま)の充実不良、貯蔵性低下が現実的に発生します。
 葉の表面に、ぼんやりとした薄暗いカビ(胞子)が発生(タマネギべと病)
葉の表面に、ぼんやりとした薄暗いカビ(胞子)が発生(タマネギべと病)
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)が圃場で引き起こす影響
発病株が増えると、健全葉の割合が低下して同化量が減り、肥大が遅れて規格外の増加や収量低下が起こり得ます。特に肥大期に向けて葉が早期に枯れ込む場合、玉の太り不足が顕著になり、圃場内での生育ムラが拡大します。
また、発生が長期間続いた圃場では、病原が罹病葉(りびょうは)などの残さに由来して次作の初期発生源となりやすく、作期初期から再発するリスクが高まります。このため、当年作だけでなく、次作を含めた作付体系全体でのリスク管理が必要になります。
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)の診断と判断基準
- 経過観察でよい状態
葉の黄化が局所的で、葉裏のかび状病徴が確認できず、症状が周辺株へ広がらない。湿度が下がると進行が鈍り、圃場の葉のぬれ時間が短い条件にある。この段階では直ちに防除は不要だが、環境変化に備えた継続観察が必要となる。 - 防除・対策が必要な状態
葉裏に灰紫色〜暗灰色のかび状病徴が確認できる、または周辺株へ同様の症状が拡大している。夜露・降雨・過湿が続き、葉のぬれ時間が長い環境が重なっている。この段階での対策目的は、枯れた葉を回復させることではなく、健全葉への感染拡大を抑えることにある。 - 回復困難・更新判断が必要な状態
圃場全体で葉の枯れ込みが進行し、健全葉が十分に確保できず、肥大期に同化能力の回復が見込めない。発生が継続しても作期的に収量回復が期待できず、当年作の延命よりも、次作のリスク低減を優先すべき段階となる。
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)の防除対策
- 耕種的防除(作期・管理による回避)
防除の基本は、葉のぬれ時間を短縮することにあります。過繁茂(かはんも)を避けて株間と通風(つうふう)を確保し、葉が長時間ぬれ続ける条件を作らない。過度な窒素多施用(たしよう)を避け、葉がやわらかく過密になる状態を抑える。圃場の排水性を確保して過湿を防ぎ、発病残さ(罹病葉など)は持ち出しや適正処理により、次作の初期発生源を残しにくくする。 - 物理的・環境的防除
施設栽培では換気(かんき)と除湿(じょしつ)によって夜間〜早朝の高湿を下げ、結露(けつろ)を減らす。ただし、環境制御だけで完全に発生を防げるわけではなく、天候条件によっては限界があるため、発生兆候の有無を継続的に確認する。かん水は葉をぬらしにくい方法を優先し、やむを得ず散水する場合は朝に行い、日中に乾く条件を作る。 - 化学的防除(適用条件・限界を必ず明示)
登録(とうろく)農薬の適用作物・希釈倍数・使用回数・収穫前日数を厳守し、発病後の「治療」を目的とせず、感染成立前後を狙った予防的散布として位置づける。同系統薬剤の連用は抵抗性(ていこうせい)リスクを高めるため、作用機作(さようきさ)の異なる薬剤をローテーションする。すでに葉の枯死が広範囲に及び、健全葉の回復が見込めない段階では、散布を継続しても収量回復につながらないため、防除の打ち切り判断が必要となる。
タマネギべと病(たまねぎべとびょう)に関する留意点と課題
- 典型的な誤判断①:黄化=肥料不足として追肥だけで済ませる
なぜ誤りか:べと病は感染性病害であり、追肥では病原体の増殖や圃場内での拡大を抑えられません。生理障害と誤認すると初動が遅れ、被害が広がります。
対処方法:葉裏のかび状病徴の有無、周辺株への拡大、葉のぬれ時間(夜露・過湿)を確認し、感染条件がそろう場合は環境改善を含む防除判断へ段階的に移行します。 - 典型的な誤判断②:葉裏の所見を確認せず、別病害(紫斑病など)として薬剤を選ぶ
なぜ誤りか:病害ごとに有効な薬剤群や適期は異なり、診断を誤ると効果が出ないだけでなく、不要な薬剤使用によるコスト増や抵抗性リスクを高めます。
対処方法:早朝など病徴が出やすい時間帯に葉裏を確認し、病斑の質、広がり方、発生条件を合わせて病害を切り分けてから対策を選択します。 - 典型的な誤判断③:発病が進んだ後に「治るはず」と散布回数を増やす
なぜ誤りか:枯死した葉は回復せず、散布回数を増やしても収量回復につながらない場合が多く、抵抗性、薬害(やくがい)、残留基準逸脱などのリスクが増します。
対処方法:健全葉の残量、作期、発生の広がり速度から費用対効果を評価し、回復が見込めない段階では当年作の延命よりも次作リスク低減(残さ処理、作付け計画見直し)を優先します。