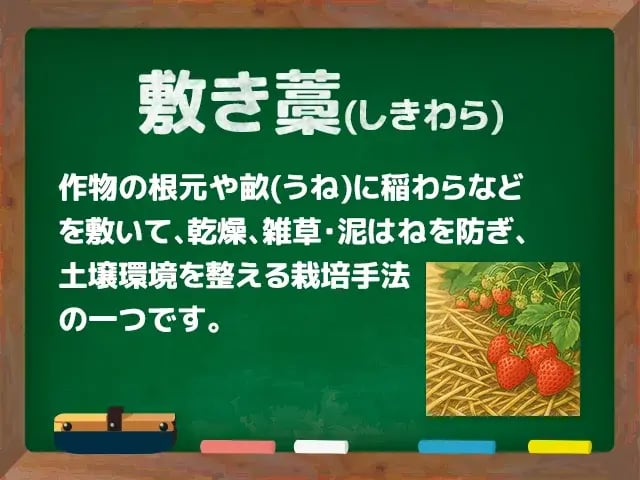
敷き藁(しきわら)とは、植物の株元や畝の表面に稲わらや麦わらを敷くことで、土壌の乾燥を防ぎ、雑草の発生を抑えるとともに、泥はねや地温の急激な変化から作物を守る農業技術です。
この手法は特に夏季の高温期や梅雨時の多湿期に有効であり、作物の健全な生育を助けます。
敷きワラは自然素材であるため、環境に優しく、分解後は堆肥として土壌の栄養源にもなります。 また、手軽に実践できるため、家庭菜園から本格的な農業まで幅広く利用されています。
同意語としては「わら敷き」「マルチング(有機マルチ)」などがあります。
敷きワラの概要
敷きワラは、稲わらや麦わらなどの植物由来の材料を用いて、作物の周囲に敷き詰める作業です。
この手法は古くから行われており、自然素材を活用した「有機マルチング」とも言えます。
その目的は多岐にわたり、地温調整、土壌水分の保持、雑草防除、病害防止、さらには美観の向上にまで及びます。
敷きワラの詳細説明
- 保湿効果
わらの層が地表を覆うことで、水分の蒸発を防ぎ、乾燥から作物を守ります。特に夏季の乾燥に強い効果があります。 - 雑草抑制
光を遮断することで雑草の発芽や成長を抑え、除草作業の手間を減らせます。 - 泥はね防止
雨や灌水時に土壌が跳ね上がることを防ぎ、作物の病気予防に役立ちます。 - 地温安定化
昼夜の温度差や寒暖差を緩和し、根へのストレスを軽減します。 - 土壌改良
分解されたわらは堆肥化され、微生物の活性を促して土壌の有機質を増加させます。
敷きワラの役割とメリット
- 自然環境への配慮
化学資材を使わずに土壌管理ができ、持続可能な農業の一助になります。 - 低コストな資材
稲作農家では副産物として手に入るため、コストを抑えた導入が可能です。 - 多用途性
夏野菜・果樹・草花・水稲など、幅広い作物に利用でき、用途に応じた工夫が可能です。
敷きワラの課題と対策
- 1. 病害虫の温床になる可能性
敷いたわらが常に湿った状態になると、カビ類や害虫の発生源になる場合があります。
対策:湿度の高い時期には定期的に乾燥させる、または耐湿性のある作物を選ぶことが有効です。
2. わらの確保が難しい地域も
都市近郊などでは稲わらが手に入りにくく、流通コストも上がる傾向があります。
対策:麦わら、落ち葉、堆肥マルチ、もみ殻など、代替素材を活用しましょう。
- 3. 長期利用による劣化
時間とともにわらが分解され、保湿や遮光の効果が薄れる場合があります。
対策:シーズンごとに補充や入れ替えを行い、適切な厚み(5~10cm)を維持することが推奨されます。








