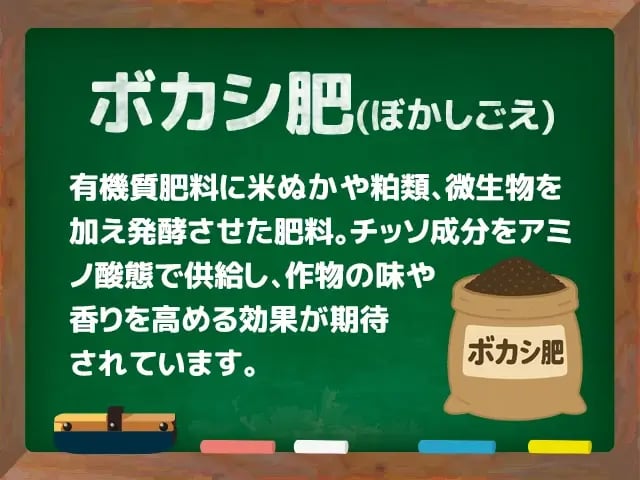
ボカシ肥(ぼかしごえ)とは、有機質肥料に米ぬかや油かす、魚かすなどの自然素材を混ぜ、微生物の力を借りて発酵(はっこう)させて作る肥料のことです。
主にチッソ成分をアミノ酸態(たい)や核酸(かくさん)として作物に供給し、作物の味や香り、色などの品質向上を目指します。水分管理を適切に行いながら、発酵を進めることで、単なる堆肥(たいひ)とは異なる、高品質な栄養源となります。
発酵過程でできたアミノ酸は、植物に吸収されやすく、健全な成長をサポートする特徴があります。最近では「Em菌入りボカシ」など、微生物資材を加えて発酵力を強化した製品もあります。
この肥料は「米ぬか発酵肥料」や「米ぬかぼかし」とも呼ばれることがあり、家庭菜園からプロ農家まで幅広く使われています。同意語としては「ぼかし肥料」「発酵肥料」などがあります。
ボカシ肥の概要
ボカシ肥は、有機質肥料をぼかす(=発酵させる)工程を通じて、植物が吸収しやすい形に変換した肥料です。代表的な材料には、米ぬか、油かす(ナタネ粕(かす)や大豆粕)、魚かす、骨粉(こっぷん)などがあり、これらを混合し水分を25%程度に調整した後、発酵菌を加えて熟成させます。ぼかす過程では、発酵熱により有害な病原菌が抑えられる効果も期待されます。
ボカシ肥の詳細説明
ボカシ肥は、有機質を主体にした資材と微生物を組み合わせることで、自然の力を活かした肥料です。ぼかす作業は、材料を均等に混ぜ、水分と温度を適正に管理することが重要です。特に、発酵中の温度は30〜50℃が理想とされ、過剰な加温や乾燥は発酵を阻害します。
作成に用いる材料は目的や地域によって様々ですが、以下のような組み合わせがよく見られます。
- 米ぬか:発酵促進と栄養源
- ナタネ粕・大豆粕:チッソ・リン酸供給源
- 魚かす:速効性チッソと微量要素
- 骨粉:リン酸とカルシウム供給
- 発酵菌(例:Em菌):微生物バランスの向上
ボカシ肥は一般的な堆肥とは異なり、チッソ成分がアミノ酸態や核酸態になっているため、作物の初期生育を助け、味・香り・色の向上に効果的です。また、配合肥料と違い、環境負荷が小さく、土壌改良(どじょうかいりょう)効果も期待できます。
ボカシ肥の役割とメリット
- 土壌改良効果
微生物の働きで土壌中の有機物が活性化され、団粒構造(だんりゅうこうぞう)の発達を促します。 - 作物の品質向上
アミノ酸態のチッソが豊富なため、野菜や果物の味や香り、色づきが良くなります。 - 環境にやさしい
化学肥料に比べて地下水汚染リスクが低く、持続可能な農業に貢献します。
ボカシ肥に関する課題と対策
1. 発酵失敗のリスク
水分管理や温度管理が適切でないと発酵がうまく進まず、腐敗臭が出たり効果が落ちることがあります。
対策:水分は25%程度、温度管理は30~50℃を維持し、適度な攪拌(かくはん)を行いましょう。
2. 材料選びの難しさ
材料のバランスが悪いと、チッソ過剰や発酵不良を引き起こす可能性があります。
対策:米ぬかや油かすを中心に、適切な比率(例:米ぬか20kg+ナタネ粕20kg+魚かす20kg)を守るとよいでしょう。
3. 熟成期間の管理
発酵が不十分なまま使用すると、根傷み(ねいたみ)や生育不良を引き起こすリスクがあります。
対策:発酵が完了し、においが甘酸っぱくなったことを確認してから施用しましょう(発酵目安:2週間~1か月程度)。








